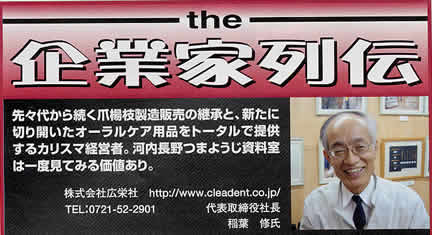
| つまようじ資料室で爪楊枝の歴史と世界観について、稲葉社長はあつく語る。 お釈迦さんの時代からインドではニームという木の枝を使って歯を清潔にすることを教えていた。しかし、中国にはこの木はなく楊柳(ようりゅう)を用いたので「ようじ」を楊(やなぎ)の枝、すなわち楊枝と書いたものが日本に伝わる。一方の房状にした部分で歯の表面をこすり、反対側の鋭くした部分で歯の間を清掃する房楊枝と呼ばれるものが江戸時代にはあった。この鋭い方を「爪の先でつまむようじ」ということから「つまようじ」の語源となる。 |
| ここ河内長野では明治16年に農家の副業として楊枝作りがはじまり集散地となった。その後、アメリカから大量に安い白樺製の「平楊枝」が入ってきて大きなダメージを受ける。祖父の時代、広栄社の前身である「東洋妻楊枝株式会社」では昭和のはじめにアメリカから機械を購入、研究を重ね機械化による生産を始めた。ところが見た目が悪い平楊枝(英語で(英語でトゥ−スピック)は日本で受け入れられず、いま我々がよく知っている丸い断面の「カクテルピック」を実用新案の新型木製機械(写真)を使って大量生産した。カクテルピックは本来料理用のものでデンタルケアには向いていない。 その後、海外では歯を守る道具として認知度が高い三角楊枝(断面が三角形でマッサージ効果もある)を生産・輸出。円高による打撃を受け、国内販売ルートの開拓をしながら、こだわりを持った独自の商品開発は続いた。 |
||
|
